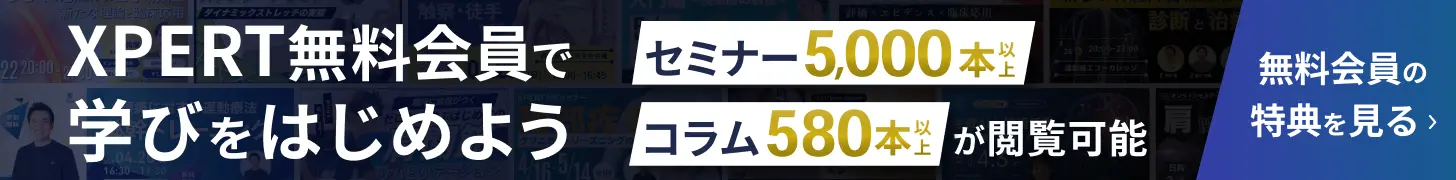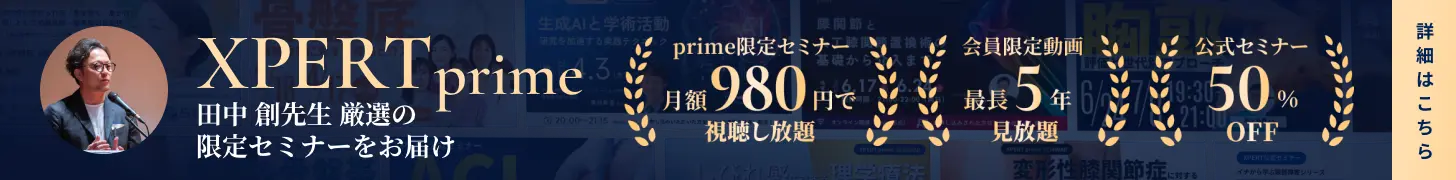「日本の高齢化をどうにかしなければいけない!」という危機感を持っている医療・介護職は多いのではないでしょうか?たしかにそうなのですが、プロフェッショナルとしてはもっと細かいアセスメントを行わなければなりません。
例えば、理学療法士の臨床では『筋力が弱い…、よし、鍛えよう!』といった短絡的なアセスメントは行わないはずです。「どこの筋肉が?」「なぜ弱いの?」「実は痛みで力が出せてないだけでは?」と思考をめぐらせるはずです。
今回のコラムでは、日本の高齢化問題に関するデータを紐解きながら、私たち医療・介護職が出来ることを考えていきます。
勉強になった!の気持ちをSNSで伝えよう
XPERTに登録しませんか?
XPERTでは、臨床の最前線で活躍する専門家の
知識やノウハウを学べます
2025/12/07 (日)掲載
【経験者急募】ピラティス歴3年以上の方へ。夜間レッスン専任で、高スキルを活かしませんか?(研修制度充実)
勤務地:福岡県福岡市西区
雇用形態:パート・アルバイト
施設形態: ヨガ/ピラティススタジオ
2025/03/05 (水)掲載
【将来独立起業を目指す理学療法士へ】月給38万~45万円 / 賞与あり / 年間休日120日以上 / 働きながら経営を学べる / 起業育成コース採用枠 | リハプライム株式会社
勤務地:埼玉県さいたま市大宮区
雇用形態:正職員
施設形態: 企業
2025/02/26 (水)掲載
運動療法に特化した自費リハビリ/年間休日125日、月収35万〜/18時終業、残業時間ほぼなし/港区広尾駅より徒歩3分
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: 診療所/クリニック