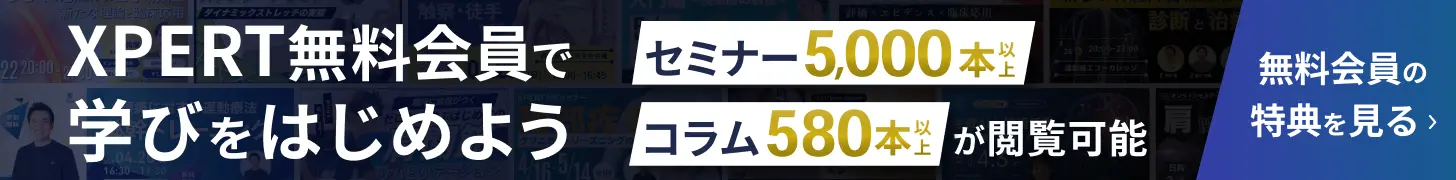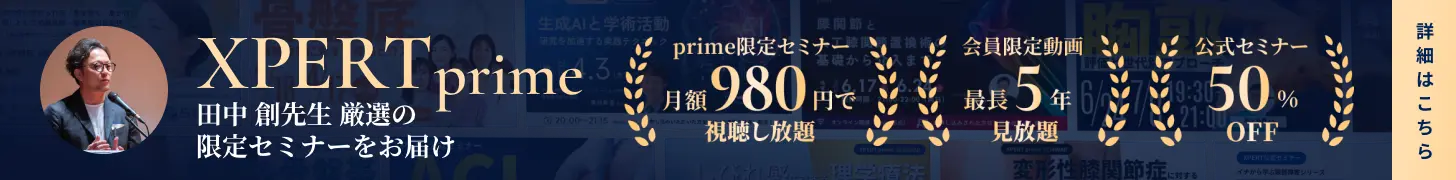先日、職場のスタッフルームでTVを見ていると「国は予防医療や介護予防にもっと予算を割くべきだ!」と強い論調で話すコメンテーターが映し出されており、同意しているスタッフが多数いました。たしかに『介護予防に取り組んでいる事業』と聞いて思い浮かべるのは、大手のフィットネスクラブなどの民間企業が行っているものですよね。
しかし、実は国が取り組んでいる介護予防事業はたくさんあります。例えば、町中にある高齢者向けのスポーツセンター・自治体の総合施設・カルチャースクールです。もしかすると、これらのために行政から依頼を受けたことがある医療・介護専門職の読者の方もいるのではないでしょうか?
今回は介護予防の考え方や取り組みについて、歴史を追いつつ整理していきます。歴史から失敗や上手くいかなかった部分を学ぶことが出来れば、これからの介護予防事業をより良いものへと作り変えていくことが出来るかもしれません。
勉強になった!の気持ちをSNSで伝えよう
XPERTに登録しませんか?
XPERTでは、臨床の最前線で活躍する専門家の
知識やノウハウを学べます
2025/12/07 (日)掲載
【経験者急募】ピラティス歴3年以上の方へ。夜間レッスン専任で、高スキルを活かしませんか?(研修制度充実)
勤務地:福岡県福岡市西区
雇用形態:パート・アルバイト
施設形態: ヨガ/ピラティススタジオ
2025/03/05 (水)掲載
【将来独立起業を目指す理学療法士へ】月給38万~45万円 / 賞与あり / 年間休日120日以上 / 働きながら経営を学べる / 起業育成コース採用枠 | リハプライム株式会社
勤務地:埼玉県さいたま市大宮区
雇用形態:正職員
施設形態: 企業
2025/02/26 (水)掲載
運動療法に特化した自費リハビリ/年間休日125日、月収35万〜/18時終業、残業時間ほぼなし/港区広尾駅より徒歩3分
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: 診療所/クリニック