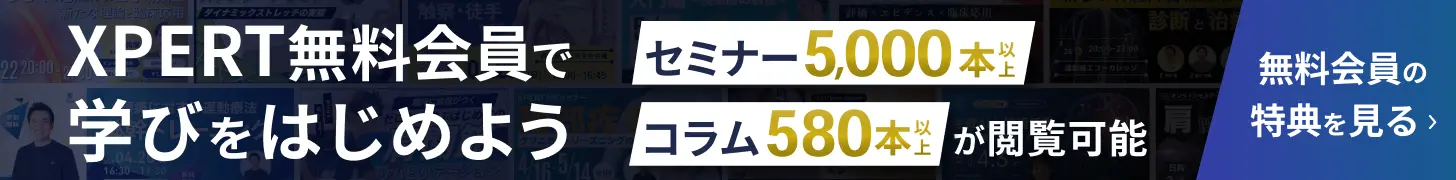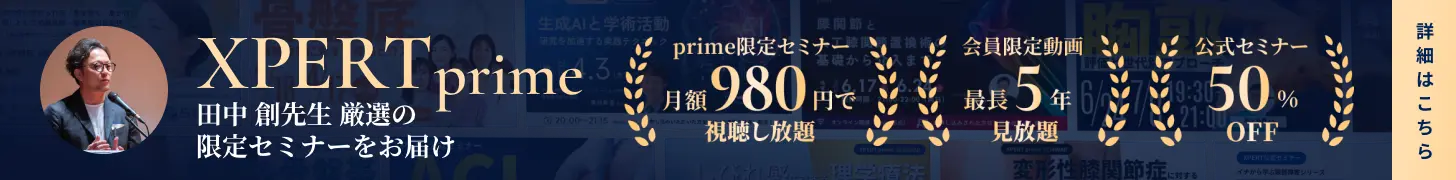脳卒中後上肢のリハビリテーションでは,American Heart/ Stroke Association(以下,AHA/ASA)のガイドライン1)では,上肢機能に影響を与える可能性がある介入方法がいくつか示されている.
そのなかで,エビデンスが最も堅固に示されたものがConstraint-Induced movement therapy(CI療法)である.
CI療法は適応基準2)から,単体の介入では上肢機能の軽度例から中等度例に限定される.しかし,近年ではロボット療法や電気刺激療法,メンタルプラクティスなど,他の介入方法や医療機器を併用することで,CI療法の効果を修飾し,より重度例まで適応が可能となる(表)1).
また,複数のシステマティックレビューに基づいたDecisional tree(図1)3)においても,主に同様な介入方法が選択されている.
本稿では,CI療法と併用される上肢機能アプローチおよび,改善した機能を長期に継続させ,より効率的に生活に汎化させる方略について紹介する.
勉強になった!の気持ちをSNSで伝えよう
XPERTに登録しませんか?
XPERTでは、臨床の最前線で活躍する専門家の
知識やノウハウを学べます
2025/12/07 (日)掲載
【経験者急募】ピラティス歴3年以上の方へ。夜間レッスン専任で、高スキルを活かしませんか?(研修制度充実)
勤務地:福岡県福岡市西区
雇用形態:パート・アルバイト
施設形態: ヨガ/ピラティススタジオ
2025/03/05 (水)掲載
【将来独立起業を目指す理学療法士へ】月給38万~45万円 / 賞与あり / 年間休日120日以上 / 働きながら経営を学べる / 起業育成コース採用枠 | リハプライム株式会社
勤務地:埼玉県さいたま市大宮区
雇用形態:正職員
施設形態: 企業
2025/02/26 (水)掲載
運動療法に特化した自費リハビリ/年間休日125日、月収35万〜/18時終業、残業時間ほぼなし/港区広尾駅より徒歩3分
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: 診療所/クリニック