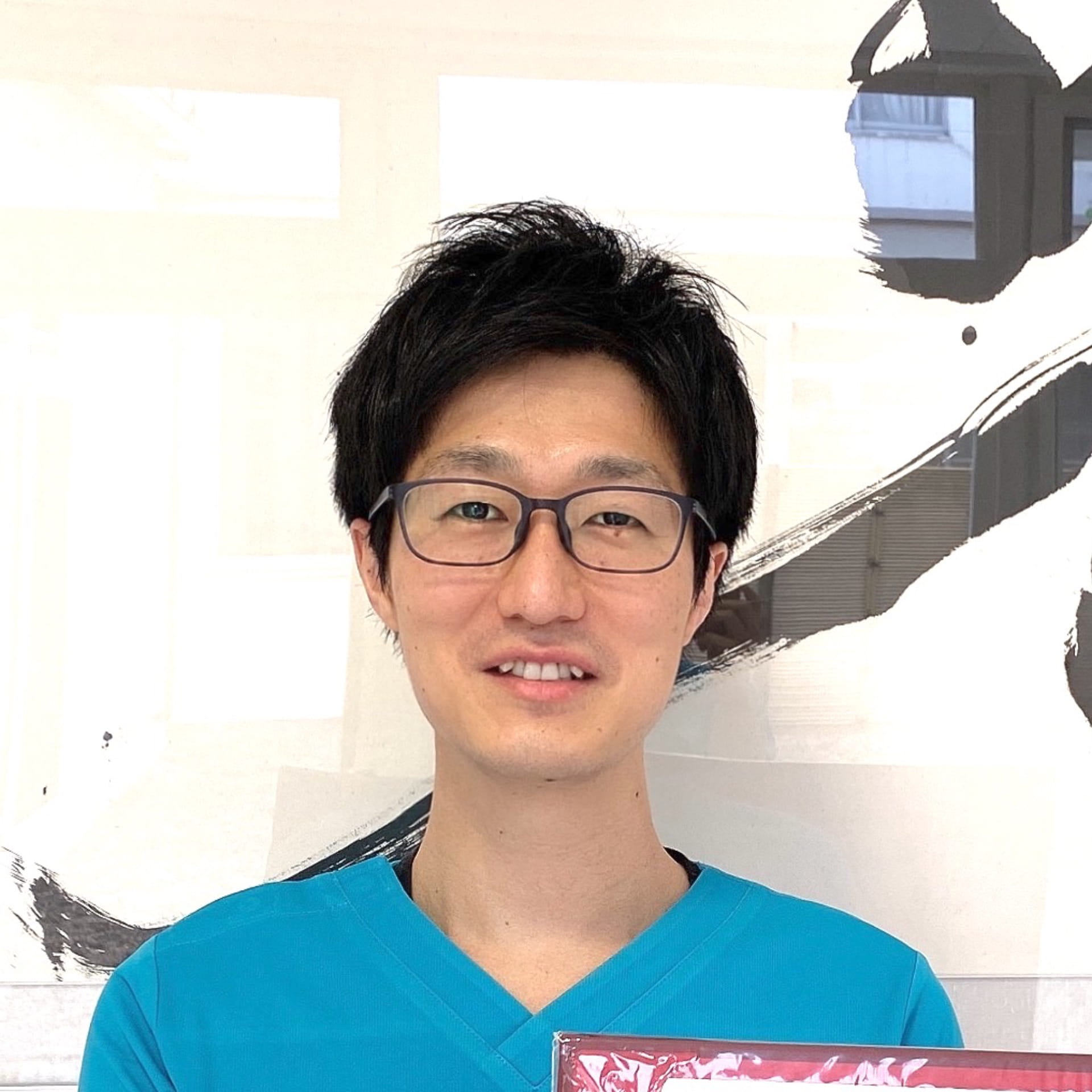前十字靭帯 (Anterior Cruciate Ligament: ACL) 損傷において、原因となる動作といえば “knee in” をよく耳にすると思います。
“knee in” とは、膝が内側に変位するといった現象です。では、本当にACL損傷時にknee inが起きているのでしょうか?またknee inのみが原因なのでしょうか?今回は、受傷時の膝関節の動きや各関節角度について少し踏み込んで解説していきます。
勉強になった!の気持ちをSNSで伝えよう
XPERTに登録しませんか?
XPERTでは、臨床の最前線で活躍する専門家の
知識やノウハウを学べます
2025/03/05 (水)掲載
【将来独立起業を目指す理学療法士へ】月給38万~45万円 / 賞与あり / 年間休日120日以上 / 働きながら経営を学べる / 起業育成コース採用枠 | リハプライム株式会社
勤務地:埼玉県さいたま市大宮区
雇用形態:正職員
施設形態: 企業
2025/02/26 (水)掲載
運動療法に特化した自費リハビリ/年間休日125日、月収35万〜/18時終業、残業時間ほぼなし/港区広尾駅より徒歩3分
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: 診療所/クリニック
1
2025/01/20 (月)掲載
2025年・春開院!オープニングスタッフ募集
リウマチ・運動器リハ、エコーに興味のある方
勤務地:東京都世田谷区
雇用形態:正職員
施設形態: 診療所/クリニック