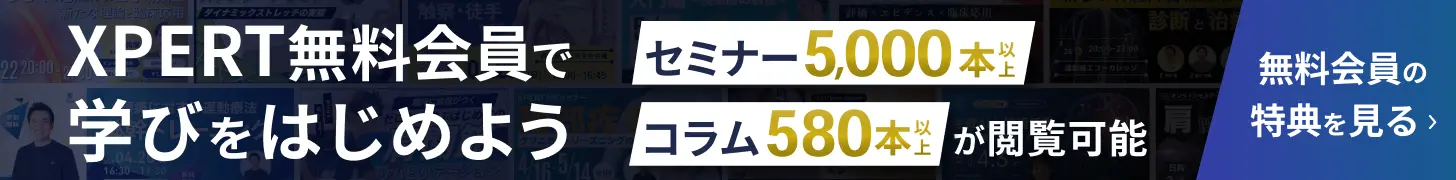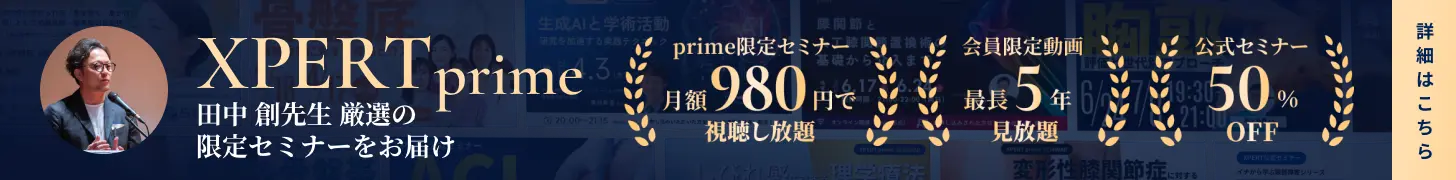生活行為向上マネジメントは,対象となる人の生活を支援する包括的な実践方法である.7段階のプロセスで構成され,3つの基本ツールと補助的なシートを用いることで,経験の浅い療法士であっても,熟練の療法士の思考過程を理解し,対象者に対してより効果的な支援を提供できるとしている.本コラムでは,各シートの特徴や実際の運用方法などを,生活行為向上マネジメントのプロセスと共に解説していく.
勉強になった!の気持ちをSNSで伝えよう
XPERTに登録しませんか?
XPERTでは、臨床の最前線で活躍する専門家の
知識やノウハウを学べます
2026/02/04 (水)掲載
【CM放映中!】長期就業&年収アップも可能! 呼吸と骨格、筋肉に着目した本質的なメソッドを学びながら働きませんか?
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: スポーツ/フィットネスクラブ
2026/02/04 (水)掲載
理学療法士・作業療法士としての想定外のキャリア!?呼吸と骨格、筋肉に着目した本質的なメソッドを学びながら働きませんか?【長期就業&年収UP可能】
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: スポーツ/フィットネスクラブ
2025/12/07 (日)掲載
【経験者急募】ピラティス歴3年以上の方へ。夜間レッスン専任で、高スキルを活かしませんか?(研修制度充実)
勤務地:福岡県福岡市西区
雇用形態:パート・アルバイト
施設形態: ヨガ/ピラティススタジオ