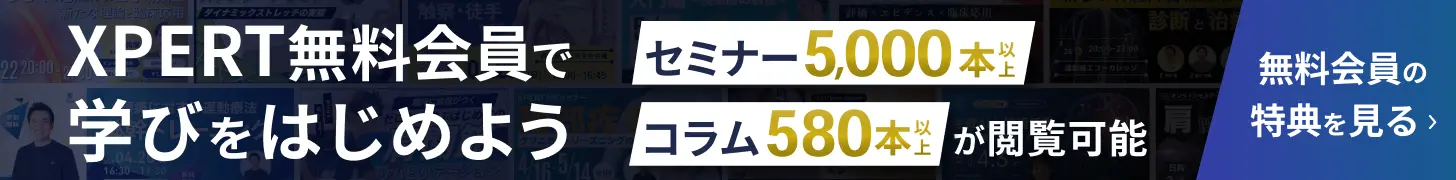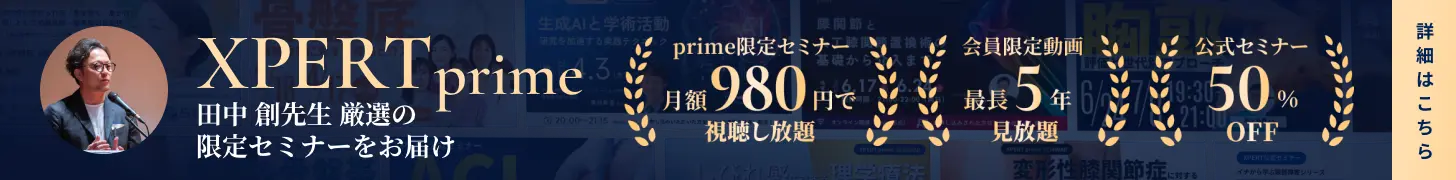仕事で課題にぶつかって、その解決方法や対策を考えるとき、(おそらく正解と思う)適切な答えを導き出すためには、様々なフレームワークがヒントになります。また、フレームワークを用いて論理立てて考えることで、言語化しやすくなり他者と共有しやすくなることもメリットです。今回は、課題解決のための代表的なフレームワークである「MECE」を読者の皆様にご紹介します。
勉強になった!の気持ちをSNSで伝えよう
XPERTに登録しませんか?
XPERTでは、臨床の最前線で活躍する専門家の
知識やノウハウを学べます
2025/12/07 (日)掲載
【経験者急募】ピラティス歴3年以上の方へ。夜間レッスン専任で、高スキルを活かしませんか?(研修制度充実)
勤務地:福岡県福岡市西区
雇用形態:パート・アルバイト
施設形態: ヨガ/ピラティススタジオ
2025/03/05 (水)掲載
【将来独立起業を目指す理学療法士へ】月給38万~45万円 / 賞与あり / 年間休日120日以上 / 働きながら経営を学べる / 起業育成コース採用枠 | リハプライム株式会社
勤務地:埼玉県さいたま市大宮区
雇用形態:正職員
施設形態: 企業
2025/02/26 (水)掲載
運動療法に特化した自費リハビリ/年間休日125日、月収35万〜/18時終業、残業時間ほぼなし/港区広尾駅より徒歩3分
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: 診療所/クリニック