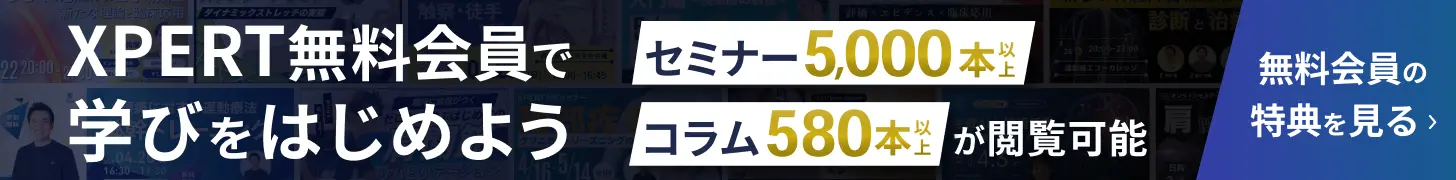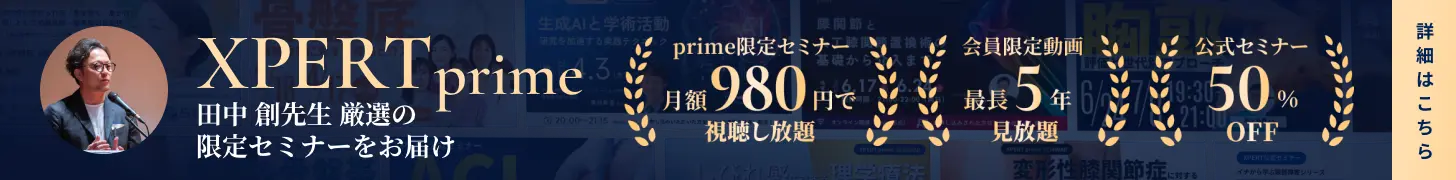我々療法士が対象者と関わる時間は、非常に限定的であることが多い。しかし、脳卒中と代謝障害を呈している対象者と関わる場合限定的な機能練習やADL練習だけでは、日常生活への汎化が難しいことも多々経験する。そこで、生活習慣の改善のための介入について解説を行う。
勉強になった!の気持ちをSNSで伝えよう
XPERTに登録しませんか?
XPERTでは、臨床の最前線で活躍する専門家の
知識やノウハウを学べます
2026/02/07 (土)掲載
作業療法士としての想定外のキャリア!?呼吸と骨格、筋肉に着目した本質的なメソッドを学びながら働きませんか?【長期就業&年収UP可能】
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: スポーツ/フィットネスクラブ
2026/02/04 (水)掲載
【CM放映中!】長期就業&年収アップも可能! 呼吸と骨格、筋肉に着目した本質的なメソッドを学びながら働きませんか?
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: スポーツ/フィットネスクラブ
2026/02/04 (水)掲載
理学療法士としての想定外のキャリア!?呼吸と骨格、筋肉に着目した本質的なメソッドを学びながら働きませんか?【長期就業&年収UP可能】
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: スポーツ/フィットネスクラブ