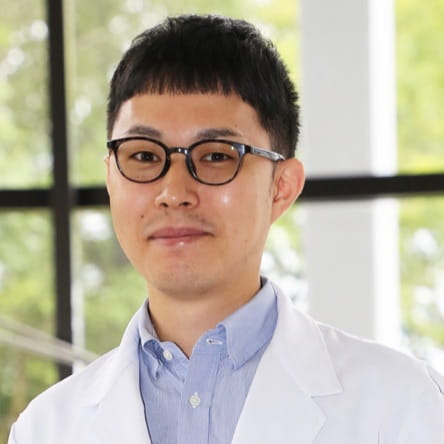ファンクショナルトレーニングにはJoint by joint theoryという考え方があります。この概念は運動に携わる仕事をしている人であれば、頭に入れておくだけで全身を俯瞰して評価・アプローチすることを可能とします。そこで今回はJoint by joint theoryについて掘り下げて紹介します。また、理学療法士とトレーナーの二足のわらじで活動している筆者が着目しているポイントも紹介します。
勉強になった!の気持ちをSNSで伝えよう
XPERTに登録しませんか?
XPERTでは、臨床の最前線で活躍する専門家の
知識やノウハウを学べます
2025/03/05 (水)掲載
【将来独立起業を目指す理学療法士へ】月給38万~45万円 / 賞与あり / 年間休日120日以上 / 働きながら経営を学べる / 起業育成コース採用枠 | リハプライム株式会社
勤務地:埼玉県さいたま市大宮区
雇用形態:正職員
施設形態: 企業
2025/02/26 (水)掲載
運動療法に特化した自費リハビリ/年間休日125日、月収35万〜/18時終業、残業時間ほぼなし/港区広尾駅より徒歩3分
勤務地:東京都港区
雇用形態:正職員
施設形態: 診療所/クリニック
1
2025/01/20 (月)掲載
2025年・春開院!オープニングスタッフ募集
リウマチ・運動器リハ、エコーに興味のある方
勤務地:東京都世田谷区
雇用形態:正職員
施設形態: 診療所/クリニック