********************
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
********************
来る7月17日より、XPERT公式セミナー「肩関節周囲炎に対する評価・治療~解剖・触診のポイントから病態に応じた病期別の対応まで~」を開催いたします
本セミナーは全5回のシリーズで構成され、肩関節周囲炎に対する評価と治療について網羅的に学ぶことができるオンラインセミナーです
肩関節周囲炎に対する評価と治療について学びたい方は、ぜひご参加ください
==============================
◾️概要
本セミナーでは、「肩関節周囲炎」に対する評価・治療について、解剖学や触診の知識を基盤としながら、病態に応じたアプローチ方法を病期別に整理し、臨床における実践力の向上を目指します
全5回にわたるシリーズ構成で、肩関節周囲炎への理解を段階的に深めていきます
第1回では、評価・治療において重要な「解剖学」の視点を取り上げ、臨床現場で活用できるポイントを解説します
第2回では、骨・筋・腱などの「触診」の技術を高めるための具体的なコツを紹介し、対象組織への正確なアプローチをサポートします
第3回では、肩関節周囲炎の「病態」を広い視野で捉えるための考え方を整理し、複雑な症例への対応力を養います
さらに第4回では、「炎症期」に絞って適切な評価法と治療戦略を解説し、急性期の症状を長引かせないための工夫を共有します
第5回では、「拘縮期」における関節可動域や日常生活動作の改善を図るための具体的な治療アプローチを紹介します
各回ともに、肩関節周囲炎の治療に関わる皆様が明日からの臨床で活かせる知識と技術の習得を目指します
◾️詳細※すべて開催後2週間のアーカイブ配信
【第1回】
・テーマ|肩関節周囲炎に対する評価や治療の根拠・視点を広げるための "解剖学" のポイント
・講師|河上 淳一先生(日本歯科大学 新潟生命歯学部 解剖学第1講座 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年7月17日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、どのような疾患でしょうか。日本肩関節学会は、可動域制限のある肩を「拘縮肩」、そのうち原因が特定できないものを「凍結肩」と定義しました(浜田 他,2021)。すなわち、明確な診断が難しく、病態も多岐にわたる疾患です。私たちは、まず対象となる構造を理解し、そこから患者に応じた評価と治療を行うことが求められます。しかし、教科書だけでは、三次元的かつ階層的なイメージの把握が難しい部位も少なくありません。本講演では、肩関節および肉眼解剖を専門とする立場から、「臨床現場に役立つ肩関節の解剖学」を解説します。次回の触診へとつながるよう、肩関節の構造理解を深めていただきたいと考えています。
(1) 肩関節の全体像
(2) 肩関節周囲の骨の特徴
(3) 肩関節筋の骨の特徴
(4) 肩関節関節包・靱帯の特徴
(5) 肩関節周囲の神経・血管の特徴
【第2回】
・テーマ|評価や治療を行う上で押さえておきたい骨・筋・腱・神経の "触診" のコツ
・講師|松本 伸一先生(古川宮田整形内科クリニック リハビリテーション科 理学療法士,医科学修士)
・日時|2025年7月31日 (木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎の診療においては、疼痛や可動域制限による機能障害が病期やその症状の程度によって求められる技術が変化します。肩甲上腕関節の運動のみでなく、肩関節複合体としての運動をとらえるためには、正確な骨運動をとらえるためのランドマークを把握することは必須の技術です。加えて、可動性が低下しやすい筋や神経の走行を理解することで、徒手療法や物理療法による介入の成果を改善し、長期の経過を良好にするために必要不可欠な運動指導やホームエクササイズを適切に指導することにもつながります。病態把握や評価・治療の精度を高めることに寄与する触診について、触診やエコー動画を交えながら理解を深めていきたいと思います。
1. 骨運動の触診
(1) 肩周囲のランドマークと触診のポイント
(2) 肩甲上腕関節の運動と触診
(3) 肩甲上腕リズムと触診(SHAに関連して)
2. 評価・治療に必要な筋・神経の触診
【第3回】
・テーマ|肩関節周囲炎の "病態" を包括的に捉える視点
・講師|隅田 涼平先生(福岡整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月7日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎,いわゆる凍結肩(Frozen shoulder)は,「既知の肩関節疾患がないのに起こる肩の自動,他動可動域の著しい制限によって特徴づけられる原因不明の疾患」とされています(Zuckerman JD ,et al,2011).肩関節周囲炎患者の訴えで最も多いのが,疼痛と可動域制限ですが,その症状や病態は様々であり,どのように介入するべきか悩むことも多いのではないでしょうか.本セミナーでは,日頃,臨床で多く遭遇する肩関節周囲炎に関して,理解しておきたい病態や病期について解説し,どのように評価・介入を行なっていくべきか理解していただければと考えています.
(1) 肩関節周囲炎の定義
(2) 肩関節周囲炎の病態
(3) 肩関節周囲炎の病期
(4) 肩関節周囲炎に対する評価
(5) 肩関節周囲炎に対する理学療法の効果
【第4回】
・テーマ|"炎症期" を見極めるための評価と症状を長引かせないための治療のコツ
・講師|鶴田 崇先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月19日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別され、好発年齢は40~60歳である。炎症期の症状は安静時も強い痛みがあり、動作時や夜間にまで増悪する。肩関節の自動運動は著しく制限され、睡眠障害を含んだ日常生活動作(ADL)の狭窄が生じる。滑膜の炎症反応が著明であり、積極的な理学療法を施すと炎症の助長を併発する恐れがある。よって、的確な理学評価と超音波機器装置などを利用した病態把握が重要であり、医師との治療方針とゴール設定の共有は大事である。
演者が臨床で各患者別に実施しているADL困難の把握方法、夜間痛に対する対処方法や活動量が多い疾患のADL拡大に繋がる評価と治療方法を紹介する。
1.炎症期の病態を理解する
1)肩関節周囲炎の病期の復習
2)炎症期に対する向き合い方
2.炎症期の病態を把握する
1)圧痛箇所による病態の把握
2)可動域制限因子の把握
3)肩甲胸郭のアライメント評価
4)姿勢および荷重変位の評価
5)カナダ作業遂行測定法(COPM)を利用した難渋しているADLの評価
3.炎症期に対する理学療法の紹介
1)各疾患に対するADL動作の紹介
2)各疾患に対するポジショニングの紹介
3)組織的過敏性を誘発させない治療戦略
4)炎症期でも可能な自主トレーニングの紹介
【第5回】
・テーマ|"拘縮期" の関節可動域・日常生活動作を拡大するためのコツ
・講師|烏山 昌起先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年9月2日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別される。炎症期を経た症例では、靱帯や関節包の線維化および瘢痕化により、生理的な弛み(遊び)が減少し、関節可動域や日常生活動作に制限が生じる。また、その上層に位置する筋腱組織でも伸張性の低下がみられるが、これには筋実質部自体の伸張性低下に加え、痛みに伴う筋収縮によって力が抜けない状態(筋緊張のコントロール不良)が混在しているのが現状である。したがって臨床では、肩関節運動の動作分析や制限因子の特定に加え、各組織の病態(短縮や攣縮など)を把握する視点も重要となる。
本セミナーでは、肩関節周囲炎の「拘縮期」に焦点を当て、演者が臨床で実践している各種評価方法(超音波評価を含む)を体系的に整理して紹介する。さらに、過敏性に応じた治療戦略を基盤に、筋短縮・筋攣縮および関節包に対する具体的なアプローチとその実際、運動療法の構成要素について解説し、より実践的な臨床応用を目指す。
1."拘縮期" の病態を理解する
(1)肩関節周囲炎における病期の復習
(2)”拘縮期"における治療対象組織
2."拘縮期"の病態を把握する
(1)肩関節痛のフローチャートによる評価
(2)姿勢および鎖骨・肩甲骨アライメントの評価
(3)肩甲上腕リズムの評価
(4)運動時痛のフローチャートによる評価
(5)肩甲上腕関節可動性と制限因子の評価
(6)筋短縮および筋攣縮の評価
(7)靱帯および関節包の評価
3."拘縮期"の病態に対する理学療法
(1)過敏性(Irritability levels)に応じた治療戦略
(2)筋短縮および筋攣縮に応じた治療戦略
(3)筋短縮および筋攣縮に対するアプローチの実際
(4)靱帯や関節包の伸張性低下に応じた治療戦略
(5)靱帯や関節包の伸張性低下に対するアプローチの実際
(6)運動療法の構成要素
(7)見落としやすい病態と対応の紹介
◾️受講目標
1. 肩関節周囲炎をみていく上で必要となる解剖学の知識を身につける
2. 肩関節周囲炎の評価・治療で必要となる骨・筋・腱の触診のポイントを理解する
3. 肩関節周囲炎の複雑な症状を病態の視点から把握する
4. 炎症期の症状に対応するために必要となる評価・治療の視点を理解する
5. 拘縮期に実践すべき評価・治療のポイントを理解する
◾️参加費
単回参加|1,980円(990円)
全回参加|6,600円(3,300円)
※()内の参加費はXPERT prime会員さま用の価格です
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
◾️注意事項
・3日前以降にキャンセルされる場合はキャンセル料100%が発生しますのでご注意ください
・配布資料は各回の開催3日前にアップいたしますので、セミナーページ下部のダウンロードリンクからダウンロードください
・各回とも開催後2週間ご視聴いただける見逃し配信を予定しています
・見逃し配信の視聴用URLはセミナー終了後にメールにてお送りいたします
・キャリアメールをご利用の場合はメールが届かない場合がございますので、GmailやYahooメールなどのフリーアドレスへの変更をお願いいたします
・メールの受信設定をご確認いただき、「 info@xpert.link 」からのメールを受信できるよう変更をお願いいたします
・セミナー終了後2~3日経過しても見逃し配信の視聴用URLがメールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認いただき、それでも確認できない場合はセミナーページ下部の「セミナーに関するお問い合わせ」からご連絡ください
開催日程
日時: 2025/07/17 (木) 20:00 - 21:30
開催場所: オンライン 講師: 河上淳一
日時: 2025/07/31 (木) 20:00 - 21:30
開催場所: オンライン 講師: 松本伸一
********************
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
********************
来る7月17日より、XPERT公式セミナー「肩関節周囲炎に対する評価・治療~解剖・触診のポイントから病態に応じた病期別の対応まで~」を開催いたします
本セミナーは全5回のシリーズで構成され、肩関節周囲炎に対する評価と治療について網羅的に学ぶことができるオンラインセミナーです
肩関節周囲炎に対する評価と治療について学びたい方は、ぜひご参加ください
==============================
◾️概要
本セミナーでは、「肩関節周囲炎」に対する評価・治療について、解剖学や触診の知識を基盤としながら、病態に応じたアプローチ方法を病期別に整理し、臨床における実践力の向上を目指します
全5回にわたるシリーズ構成で、肩関節周囲炎への理解を段階的に深めていきます
第1回では、評価・治療において重要な「解剖学」の視点を取り上げ、臨床現場で活用できるポイントを解説します
第2回では、骨・筋・腱などの「触診」の技術を高めるための具体的なコツを紹介し、対象組織への正確なアプローチをサポートします
第3回では、肩関節周囲炎の「病態」を広い視野で捉えるための考え方を整理し、複雑な症例への対応力を養います
さらに第4回では、「炎症期」に絞って適切な評価法と治療戦略を解説し、急性期の症状を長引かせないための工夫を共有します
第5回では、「拘縮期」における関節可動域や日常生活動作の改善を図るための具体的な治療アプローチを紹介します
各回ともに、肩関節周囲炎の治療に関わる皆様が明日からの臨床で活かせる知識と技術の習得を目指します
◾️詳細※すべて開催後2週間のアーカイブ配信
【第1回】
・テーマ|肩関節周囲炎に対する評価や治療の根拠・視点を広げるための "解剖学" のポイント
・講師|河上 淳一先生(日本歯科大学 新潟生命歯学部 解剖学第1講座 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年7月17日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、どのような疾患でしょうか。日本肩関節学会は、可動域制限のある肩を「拘縮肩」、そのうち原因が特定できないものを「凍結肩」と定義しました(浜田 他,2021)。すなわち、明確な診断が難しく、病態も多岐にわたる疾患です。私たちは、まず対象となる構造を理解し、そこから患者に応じた評価と治療を行うことが求められます。しかし、教科書だけでは、三次元的かつ階層的なイメージの把握が難しい部位も少なくありません。本講演では、肩関節および肉眼解剖を専門とする立場から、「臨床現場に役立つ肩関節の解剖学」を解説します。次回の触診へとつながるよう、肩関節の構造理解を深めていただきたいと考えています。
(1) 肩関節の全体像
(2) 肩関節周囲の骨の特徴
(3) 肩関節筋の骨の特徴
(4) 肩関節関節包・靱帯の特徴
(5) 肩関節周囲の神経・血管の特徴
【第2回】
・テーマ|評価や治療を行う上で押さえておきたい骨・筋・腱・神経の "触診" のコツ
・講師|松本 伸一先生(古川宮田整形内科クリニック リハビリテーション科 理学療法士,医科学修士)
・日時|2025年7月31日 (木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎の診療においては、疼痛や可動域制限による機能障害が病期やその症状の程度によって求められる技術が変化します。肩甲上腕関節の運動のみでなく、肩関節複合体としての運動をとらえるためには、正確な骨運動をとらえるためのランドマークを把握することは必須の技術です。加えて、可動性が低下しやすい筋や神経の走行を理解することで、徒手療法や物理療法による介入の成果を改善し、長期の経過を良好にするために必要不可欠な運動指導やホームエクササイズを適切に指導することにもつながります。病態把握や評価・治療の精度を高めることに寄与する触診について、触診やエコー動画を交えながら理解を深めていきたいと思います。
1. 骨運動の触診
(1) 肩周囲のランドマークと触診のポイント
(2) 肩甲上腕関節の運動と触診
(3) 肩甲上腕リズムと触診(SHAに関連して)
2. 評価・治療に必要な筋・神経の触診
【第3回】
・テーマ|肩関節周囲炎の "病態" を包括的に捉える視点
・講師|隅田 涼平先生(福岡整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月7日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎,いわゆる凍結肩(Frozen shoulder)は,「既知の肩関節疾患がないのに起こる肩の自動,他動可動域の著しい制限によって特徴づけられる原因不明の疾患」とされています(Zuckerman JD ,et al,2011).肩関節周囲炎患者の訴えで最も多いのが,疼痛と可動域制限ですが,その症状や病態は様々であり,どのように介入するべきか悩むことも多いのではないでしょうか.本セミナーでは,日頃,臨床で多く遭遇する肩関節周囲炎に関して,理解しておきたい病態や病期について解説し,どのように評価・介入を行なっていくべきか理解していただければと考えています.
(1) 肩関節周囲炎の定義
(2) 肩関節周囲炎の病態
(3) 肩関節周囲炎の病期
(4) 肩関節周囲炎に対する評価
(5) 肩関節周囲炎に対する理学療法の効果
【第4回】
・テーマ|"炎症期" を見極めるための評価と症状を長引かせないための治療のコツ
・講師|鶴田 崇先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月19日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別され、好発年齢は40~60歳である。炎症期の症状は安静時も強い痛みがあり、動作時や夜間にまで増悪する。肩関節の自動運動は著しく制限され、睡眠障害を含んだ日常生活動作(ADL)の狭窄が生じる。滑膜の炎症反応が著明であり、積極的な理学療法を施すと炎症の助長を併発する恐れがある。よって、的確な理学評価と超音波機器装置などを利用した病態把握が重要であり、医師との治療方針とゴール設定の共有は大事である。
演者が臨床で各患者別に実施しているADL困難の把握方法、夜間痛に対する対処方法や活動量が多い疾患のADL拡大に繋がる評価と治療方法を紹介する。
1.炎症期の病態を理解する
1)肩関節周囲炎の病期の復習
2)炎症期に対する向き合い方
2.炎症期の病態を把握する
1)圧痛箇所による病態の把握
2)可動域制限因子の把握
3)肩甲胸郭のアライメント評価
4)姿勢および荷重変位の評価
5)カナダ作業遂行測定法(COPM)を利用した難渋しているADLの評価
3.炎症期に対する理学療法の紹介
1)各疾患に対するADL動作の紹介
2)各疾患に対するポジショニングの紹介
3)組織的過敏性を誘発させない治療戦略
4)炎症期でも可能な自主トレーニングの紹介
【第5回】
・テーマ|"拘縮期" の関節可動域・日常生活動作を拡大するためのコツ
・講師|烏山 昌起先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年9月2日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別される。炎症期を経た症例では、靱帯や関節包の線維化および瘢痕化により、生理的な弛み(遊び)が減少し、関節可動域や日常生活動作に制限が生じる。また、その上層に位置する筋腱組織でも伸張性の低下がみられるが、これには筋実質部自体の伸張性低下に加え、痛みに伴う筋収縮によって力が抜けない状態(筋緊張のコントロール不良)が混在しているのが現状である。したがって臨床では、肩関節運動の動作分析や制限因子の特定に加え、各組織の病態(短縮や攣縮など)を把握する視点も重要となる。
本セミナーでは、肩関節周囲炎の「拘縮期」に焦点を当て、演者が臨床で実践している各種評価方法(超音波評価を含む)を体系的に整理して紹介する。さらに、過敏性に応じた治療戦略を基盤に、筋短縮・筋攣縮および関節包に対する具体的なアプローチとその実際、運動療法の構成要素について解説し、より実践的な臨床応用を目指す。
1."拘縮期" の病態を理解する
(1)肩関節周囲炎における病期の復習
(2)”拘縮期"における治療対象組織
2."拘縮期"の病態を把握する
(1)肩関節痛のフローチャートによる評価
(2)姿勢および鎖骨・肩甲骨アライメントの評価
(3)肩甲上腕リズムの評価
(4)運動時痛のフローチャートによる評価
(5)肩甲上腕関節可動性と制限因子の評価
(6)筋短縮および筋攣縮の評価
(7)靱帯および関節包の評価
3."拘縮期"の病態に対する理学療法
(1)過敏性(Irritability levels)に応じた治療戦略
(2)筋短縮および筋攣縮に応じた治療戦略
(3)筋短縮および筋攣縮に対するアプローチの実際
(4)靱帯や関節包の伸張性低下に応じた治療戦略
(5)靱帯や関節包の伸張性低下に対するアプローチの実際
(6)運動療法の構成要素
(7)見落としやすい病態と対応の紹介
◾️受講目標
1. 肩関節周囲炎をみていく上で必要となる解剖学の知識を身につける
2. 肩関節周囲炎の評価・治療で必要となる骨・筋・腱の触診のポイントを理解する
3. 肩関節周囲炎の複雑な症状を病態の視点から把握する
4. 炎症期の症状に対応するために必要となる評価・治療の視点を理解する
5. 拘縮期に実践すべき評価・治療のポイントを理解する
◾️参加費
単回参加|1,980円(990円)
全回参加|6,600円(3,300円)
※()内の参加費はXPERT prime会員さま用の価格です
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
◾️注意事項
・3日前以降にキャンセルされる場合はキャンセル料100%が発生しますのでご注意ください
・配布資料は各回の開催3日前にアップいたしますので、セミナーページ下部のダウンロードリンクからダウンロードください
・各回とも開催後2週間ご視聴いただける見逃し配信を予定しています
・見逃し配信の視聴用URLはセミナー終了後にメールにてお送りいたします
・キャリアメールをご利用の場合はメールが届かない場合がございますので、GmailやYahooメールなどのフリーアドレスへの変更をお願いいたします
・メールの受信設定をご確認いただき、「 info@xpert.link 」からのメールを受信できるよう変更をお願いいたします
・セミナー終了後2~3日経過しても見逃し配信の視聴用URLがメールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認いただき、それでも確認できない場合はセミナーページ下部の「セミナーに関するお問い合わせ」からご連絡ください日時: 2025/08/07 (木) 20:00 - 21:30
開催場所: オンライン 講師: 隅田涼平
********************
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
********************
来る7月17日より、XPERT公式セミナー「肩関節周囲炎に対する評価・治療~解剖・触診のポイントから病態に応じた病期別の対応まで~」を開催いたします
本セミナーは全5回のシリーズで構成され、肩関節周囲炎に対する評価と治療について網羅的に学ぶことができるオンラインセミナーです
肩関節周囲炎に対する評価と治療について学びたい方は、ぜひご参加ください
==============================
◾️概要
本セミナーでは、「肩関節周囲炎」に対する評価・治療について、解剖学や触診の知識を基盤としながら、病態に応じたアプローチ方法を病期別に整理し、臨床における実践力の向上を目指します
全5回にわたるシリーズ構成で、肩関節周囲炎への理解を段階的に深めていきます
第1回では、評価・治療において重要な「解剖学」の視点を取り上げ、臨床現場で活用できるポイントを解説します
第2回では、骨・筋・腱などの「触診」の技術を高めるための具体的なコツを紹介し、対象組織への正確なアプローチをサポートします
第3回では、肩関節周囲炎の「病態」を広い視野で捉えるための考え方を整理し、複雑な症例への対応力を養います
さらに第4回では、「炎症期」に絞って適切な評価法と治療戦略を解説し、急性期の症状を長引かせないための工夫を共有します
第5回では、「拘縮期」における関節可動域や日常生活動作の改善を図るための具体的な治療アプローチを紹介します
各回ともに、肩関節周囲炎の治療に関わる皆様が明日からの臨床で活かせる知識と技術の習得を目指します
◾️詳細※すべて開催後2週間のアーカイブ配信
【第1回】
・テーマ|肩関節周囲炎に対する評価や治療の根拠・視点を広げるための "解剖学" のポイント
・講師|河上 淳一先生(日本歯科大学 新潟生命歯学部 解剖学第1講座 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年7月17日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、どのような疾患でしょうか。日本肩関節学会は、可動域制限のある肩を「拘縮肩」、そのうち原因が特定できないものを「凍結肩」と定義しました(浜田 他,2021)。すなわち、明確な診断が難しく、病態も多岐にわたる疾患です。私たちは、まず対象となる構造を理解し、そこから患者に応じた評価と治療を行うことが求められます。しかし、教科書だけでは、三次元的かつ階層的なイメージの把握が難しい部位も少なくありません。本講演では、肩関節および肉眼解剖を専門とする立場から、「臨床現場に役立つ肩関節の解剖学」を解説します。次回の触診へとつながるよう、肩関節の構造理解を深めていただきたいと考えています。
(1) 肩関節の全体像
(2) 肩関節周囲の骨の特徴
(3) 肩関節筋の骨の特徴
(4) 肩関節関節包・靱帯の特徴
(5) 肩関節周囲の神経・血管の特徴
【第2回】
・テーマ|評価や治療を行う上で押さえておきたい骨・筋・腱・神経の "触診" のコツ
・講師|松本 伸一先生(古川宮田整形内科クリニック リハビリテーション科 理学療法士,医科学修士)
・日時|2025年7月31日 (木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎の診療においては、疼痛や可動域制限による機能障害が病期やその症状の程度によって求められる技術が変化します。肩甲上腕関節の運動のみでなく、肩関節複合体としての運動をとらえるためには、正確な骨運動をとらえるためのランドマークを把握することは必須の技術です。加えて、可動性が低下しやすい筋や神経の走行を理解することで、徒手療法や物理療法による介入の成果を改善し、長期の経過を良好にするために必要不可欠な運動指導やホームエクササイズを適切に指導することにもつながります。病態把握や評価・治療の精度を高めることに寄与する触診について、触診やエコー動画を交えながら理解を深めていきたいと思います。
1. 骨運動の触診
(1) 肩周囲のランドマークと触診のポイント
(2) 肩甲上腕関節の運動と触診
(3) 肩甲上腕リズムと触診(SHAに関連して)
2. 評価・治療に必要な筋・神経の触診
【第3回】
・テーマ|肩関節周囲炎の "病態" を包括的に捉える視点
・講師|隅田 涼平先生(福岡整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月7日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎,いわゆる凍結肩(Frozen shoulder)は,「既知の肩関節疾患がないのに起こる肩の自動,他動可動域の著しい制限によって特徴づけられる原因不明の疾患」とされています(Zuckerman JD ,et al,2011).肩関節周囲炎患者の訴えで最も多いのが,疼痛と可動域制限ですが,その症状や病態は様々であり,どのように介入するべきか悩むことも多いのではないでしょうか.本セミナーでは,日頃,臨床で多く遭遇する肩関節周囲炎に関して,理解しておきたい病態や病期について解説し,どのように評価・介入を行なっていくべきか理解していただければと考えています.
(1) 肩関節周囲炎の定義
(2) 肩関節周囲炎の病態
(3) 肩関節周囲炎の病期
(4) 肩関節周囲炎に対する評価
(5) 肩関節周囲炎に対する理学療法の効果
【第4回】
・テーマ|"炎症期" を見極めるための評価と症状を長引かせないための治療のコツ
・講師|鶴田 崇先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月19日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別され、好発年齢は40~60歳である。炎症期の症状は安静時も強い痛みがあり、動作時や夜間にまで増悪する。肩関節の自動運動は著しく制限され、睡眠障害を含んだ日常生活動作(ADL)の狭窄が生じる。滑膜の炎症反応が著明であり、積極的な理学療法を施すと炎症の助長を併発する恐れがある。よって、的確な理学評価と超音波機器装置などを利用した病態把握が重要であり、医師との治療方針とゴール設定の共有は大事である。
演者が臨床で各患者別に実施しているADL困難の把握方法、夜間痛に対する対処方法や活動量が多い疾患のADL拡大に繋がる評価と治療方法を紹介する。
1.炎症期の病態を理解する
1)肩関節周囲炎の病期の復習
2)炎症期に対する向き合い方
2.炎症期の病態を把握する
1)圧痛箇所による病態の把握
2)可動域制限因子の把握
3)肩甲胸郭のアライメント評価
4)姿勢および荷重変位の評価
5)カナダ作業遂行測定法(COPM)を利用した難渋しているADLの評価
3.炎症期に対する理学療法の紹介
1)各疾患に対するADL動作の紹介
2)各疾患に対するポジショニングの紹介
3)組織的過敏性を誘発させない治療戦略
4)炎症期でも可能な自主トレーニングの紹介
【第5回】
・テーマ|"拘縮期" の関節可動域・日常生活動作を拡大するためのコツ
・講師|烏山 昌起先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年9月2日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別される。炎症期を経た症例では、靱帯や関節包の線維化および瘢痕化により、生理的な弛み(遊び)が減少し、関節可動域や日常生活動作に制限が生じる。また、その上層に位置する筋腱組織でも伸張性の低下がみられるが、これには筋実質部自体の伸張性低下に加え、痛みに伴う筋収縮によって力が抜けない状態(筋緊張のコントロール不良)が混在しているのが現状である。したがって臨床では、肩関節運動の動作分析や制限因子の特定に加え、各組織の病態(短縮や攣縮など)を把握する視点も重要となる。
本セミナーでは、肩関節周囲炎の「拘縮期」に焦点を当て、演者が臨床で実践している各種評価方法(超音波評価を含む)を体系的に整理して紹介する。さらに、過敏性に応じた治療戦略を基盤に、筋短縮・筋攣縮および関節包に対する具体的なアプローチとその実際、運動療法の構成要素について解説し、より実践的な臨床応用を目指す。
1."拘縮期" の病態を理解する
(1)肩関節周囲炎における病期の復習
(2)”拘縮期"における治療対象組織
2."拘縮期"の病態を把握する
(1)肩関節痛のフローチャートによる評価
(2)姿勢および鎖骨・肩甲骨アライメントの評価
(3)肩甲上腕リズムの評価
(4)運動時痛のフローチャートによる評価
(5)肩甲上腕関節可動性と制限因子の評価
(6)筋短縮および筋攣縮の評価
(7)靱帯および関節包の評価
3."拘縮期"の病態に対する理学療法
(1)過敏性(Irritability levels)に応じた治療戦略
(2)筋短縮および筋攣縮に応じた治療戦略
(3)筋短縮および筋攣縮に対するアプローチの実際
(4)靱帯や関節包の伸張性低下に応じた治療戦略
(5)靱帯や関節包の伸張性低下に対するアプローチの実際
(6)運動療法の構成要素
(7)見落としやすい病態と対応の紹介
◾️受講目標
1. 肩関節周囲炎をみていく上で必要となる解剖学の知識を身につける
2. 肩関節周囲炎の評価・治療で必要となる骨・筋・腱の触診のポイントを理解する
3. 肩関節周囲炎の複雑な症状を病態の視点から把握する
4. 炎症期の症状に対応するために必要となる評価・治療の視点を理解する
5. 拘縮期に実践すべき評価・治療のポイントを理解する
◾️参加費
単回参加|1,980円(990円)
全回参加|6,600円(3,300円)
※()内の参加費はXPERT prime会員さま用の価格です
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
◾️注意事項
・3日前以降にキャンセルされる場合はキャンセル料100%が発生しますのでご注意ください
・配布資料は各回の開催3日前にアップいたしますので、セミナーページ下部のダウンロードリンクからダウンロードください
・各回とも開催後2週間ご視聴いただける見逃し配信を予定しています
・見逃し配信の視聴用URLはセミナー終了後にメールにてお送りいたします
・キャリアメールをご利用の場合はメールが届かない場合がございますので、GmailやYahooメールなどのフリーアドレスへの変更をお願いいたします
・メールの受信設定をご確認いただき、「 info@xpert.link 」からのメールを受信できるよう変更をお願いいたします
・セミナー終了後2~3日経過しても見逃し配信の視聴用URLがメールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認いただき、それでも確認できない場合はセミナーページ下部の「セミナーに関するお問い合わせ」からご連絡ください日時: 2025/08/19 (火) 20:00 - 21:30
開催場所: オンライン 講師: 鶴田 崇
********************
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
********************
来る7月17日より、XPERT公式セミナー「肩関節周囲炎に対する評価・治療~解剖・触診のポイントから病態に応じた病期別の対応まで~」を開催いたします
本セミナーは全5回のシリーズで構成され、肩関節周囲炎に対する評価と治療について網羅的に学ぶことができるオンラインセミナーです
肩関節周囲炎に対する評価と治療について学びたい方は、ぜひご参加ください
==============================
◾️概要
本セミナーでは、「肩関節周囲炎」に対する評価・治療について、解剖学や触診の知識を基盤としながら、病態に応じたアプローチ方法を病期別に整理し、臨床における実践力の向上を目指します
全5回にわたるシリーズ構成で、肩関節周囲炎への理解を段階的に深めていきます
第1回では、評価・治療において重要な「解剖学」の視点を取り上げ、臨床現場で活用できるポイントを解説します
第2回では、骨・筋・腱などの「触診」の技術を高めるための具体的なコツを紹介し、対象組織への正確なアプローチをサポートします
第3回では、肩関節周囲炎の「病態」を広い視野で捉えるための考え方を整理し、複雑な症例への対応力を養います
さらに第4回では、「炎症期」に絞って適切な評価法と治療戦略を解説し、急性期の症状を長引かせないための工夫を共有します
第5回では、「拘縮期」における関節可動域や日常生活動作の改善を図るための具体的な治療アプローチを紹介します
各回ともに、肩関節周囲炎の治療に関わる皆様が明日からの臨床で活かせる知識と技術の習得を目指します
◾️詳細※すべて開催後2週間のアーカイブ配信
【第1回】
・テーマ|肩関節周囲炎に対する評価や治療の根拠・視点を広げるための "解剖学" のポイント
・講師|河上 淳一先生(日本歯科大学 新潟生命歯学部 解剖学第1講座 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年7月17日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、どのような疾患でしょうか。日本肩関節学会は、可動域制限のある肩を「拘縮肩」、そのうち原因が特定できないものを「凍結肩」と定義しました(浜田 他,2021)。すなわち、明確な診断が難しく、病態も多岐にわたる疾患です。私たちは、まず対象となる構造を理解し、そこから患者に応じた評価と治療を行うことが求められます。しかし、教科書だけでは、三次元的かつ階層的なイメージの把握が難しい部位も少なくありません。本講演では、肩関節および肉眼解剖を専門とする立場から、「臨床現場に役立つ肩関節の解剖学」を解説します。次回の触診へとつながるよう、肩関節の構造理解を深めていただきたいと考えています。
(1) 肩関節の全体像
(2) 肩関節周囲の骨の特徴
(3) 肩関節筋の骨の特徴
(4) 肩関節関節包・靱帯の特徴
(5) 肩関節周囲の神経・血管の特徴
【第2回】
・テーマ|評価や治療を行う上で押さえておきたい骨・筋・腱・神経の "触診" のコツ
・講師|松本 伸一先生(古川宮田整形内科クリニック リハビリテーション科 理学療法士,医科学修士)
・日時|2025年7月31日 (木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎の診療においては、疼痛や可動域制限による機能障害が病期やその症状の程度によって求められる技術が変化します。肩甲上腕関節の運動のみでなく、肩関節複合体としての運動をとらえるためには、正確な骨運動をとらえるためのランドマークを把握することは必須の技術です。加えて、可動性が低下しやすい筋や神経の走行を理解することで、徒手療法や物理療法による介入の成果を改善し、長期の経過を良好にするために必要不可欠な運動指導やホームエクササイズを適切に指導することにもつながります。病態把握や評価・治療の精度を高めることに寄与する触診について、触診やエコー動画を交えながら理解を深めていきたいと思います。
1. 骨運動の触診
(1) 肩周囲のランドマークと触診のポイント
(2) 肩甲上腕関節の運動と触診
(3) 肩甲上腕リズムと触診(SHAに関連して)
2. 評価・治療に必要な筋・神経の触診
【第3回】
・テーマ|肩関節周囲炎の "病態" を包括的に捉える視点
・講師|隅田 涼平先生(福岡整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月7日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎,いわゆる凍結肩(Frozen shoulder)は,「既知の肩関節疾患がないのに起こる肩の自動,他動可動域の著しい制限によって特徴づけられる原因不明の疾患」とされています(Zuckerman JD ,et al,2011).肩関節周囲炎患者の訴えで最も多いのが,疼痛と可動域制限ですが,その症状や病態は様々であり,どのように介入するべきか悩むことも多いのではないでしょうか.本セミナーでは,日頃,臨床で多く遭遇する肩関節周囲炎に関して,理解しておきたい病態や病期について解説し,どのように評価・介入を行なっていくべきか理解していただければと考えています.
(1) 肩関節周囲炎の定義
(2) 肩関節周囲炎の病態
(3) 肩関節周囲炎の病期
(4) 肩関節周囲炎に対する評価
(5) 肩関節周囲炎に対する理学療法の効果
【第4回】
・テーマ|"炎症期" を見極めるための評価と症状を長引かせないための治療のコツ
・講師|鶴田 崇先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月19日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別され、好発年齢は40~60歳である。炎症期の症状は安静時も強い痛みがあり、動作時や夜間にまで増悪する。肩関節の自動運動は著しく制限され、睡眠障害を含んだ日常生活動作(ADL)の狭窄が生じる。滑膜の炎症反応が著明であり、積極的な理学療法を施すと炎症の助長を併発する恐れがある。よって、的確な理学評価と超音波機器装置などを利用した病態把握が重要であり、医師との治療方針とゴール設定の共有は大事である。
演者が臨床で各患者別に実施しているADL困難の把握方法、夜間痛に対する対処方法や活動量が多い疾患のADL拡大に繋がる評価と治療方法を紹介する。
1.炎症期の病態を理解する
1)肩関節周囲炎の病期の復習
2)炎症期に対する向き合い方
2.炎症期の病態を把握する
1)圧痛箇所による病態の把握
2)可動域制限因子の把握
3)肩甲胸郭のアライメント評価
4)姿勢および荷重変位の評価
5)カナダ作業遂行測定法(COPM)を利用した難渋しているADLの評価
3.炎症期に対する理学療法の紹介
1)各疾患に対するADL動作の紹介
2)各疾患に対するポジショニングの紹介
3)組織的過敏性を誘発させない治療戦略
4)炎症期でも可能な自主トレーニングの紹介
【第5回】
・テーマ|"拘縮期" の関節可動域・日常生活動作を拡大するためのコツ
・講師|烏山 昌起先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年9月2日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別される。炎症期を経た症例では、靱帯や関節包の線維化および瘢痕化により、生理的な弛み(遊び)が減少し、関節可動域や日常生活動作に制限が生じる。また、その上層に位置する筋腱組織でも伸張性の低下がみられるが、これには筋実質部自体の伸張性低下に加え、痛みに伴う筋収縮によって力が抜けない状態(筋緊張のコントロール不良)が混在しているのが現状である。したがって臨床では、肩関節運動の動作分析や制限因子の特定に加え、各組織の病態(短縮や攣縮など)を把握する視点も重要となる。
本セミナーでは、肩関節周囲炎の「拘縮期」に焦点を当て、演者が臨床で実践している各種評価方法(超音波評価を含む)を体系的に整理して紹介する。さらに、過敏性に応じた治療戦略を基盤に、筋短縮・筋攣縮および関節包に対する具体的なアプローチとその実際、運動療法の構成要素について解説し、より実践的な臨床応用を目指す。
1."拘縮期" の病態を理解する
(1)肩関節周囲炎における病期の復習
(2)”拘縮期"における治療対象組織
2."拘縮期"の病態を把握する
(1)肩関節痛のフローチャートによる評価
(2)姿勢および鎖骨・肩甲骨アライメントの評価
(3)肩甲上腕リズムの評価
(4)運動時痛のフローチャートによる評価
(5)肩甲上腕関節可動性と制限因子の評価
(6)筋短縮および筋攣縮の評価
(7)靱帯および関節包の評価
3."拘縮期"の病態に対する理学療法
(1)過敏性(Irritability levels)に応じた治療戦略
(2)筋短縮および筋攣縮に応じた治療戦略
(3)筋短縮および筋攣縮に対するアプローチの実際
(4)靱帯や関節包の伸張性低下に応じた治療戦略
(5)靱帯や関節包の伸張性低下に対するアプローチの実際
(6)運動療法の構成要素
(7)見落としやすい病態と対応の紹介
◾️受講目標
1. 肩関節周囲炎をみていく上で必要となる解剖学の知識を身につける
2. 肩関節周囲炎の評価・治療で必要となる骨・筋・腱の触診のポイントを理解する
3. 肩関節周囲炎の複雑な症状を病態の視点から把握する
4. 炎症期の症状に対応するために必要となる評価・治療の視点を理解する
5. 拘縮期に実践すべき評価・治療のポイントを理解する
◾️参加費
単回参加|1,980円(990円)
全回参加|6,600円(3,300円)
※()内の参加費はXPERT prime会員さま用の価格です
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
◾️注意事項
・3日前以降にキャンセルされる場合はキャンセル料100%が発生しますのでご注意ください
・配布資料は各回の開催3日前にアップいたしますので、セミナーページ下部のダウンロードリンクからダウンロードください
・各回とも開催後2週間ご視聴いただける見逃し配信を予定しています
・見逃し配信の視聴用URLはセミナー終了後にメールにてお送りいたします
・キャリアメールをご利用の場合はメールが届かない場合がございますので、GmailやYahooメールなどのフリーアドレスへの変更をお願いいたします
・メールの受信設定をご確認いただき、「 info@xpert.link 」からのメールを受信できるよう変更をお願いいたします
・セミナー終了後2~3日経過しても見逃し配信の視聴用URLがメールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認いただき、それでも確認できない場合はセミナーページ下部の「セミナーに関するお問い合わせ」からご連絡ください日時: 2025/09/02 (火) 20:00 - 21:30
開催場所: オンライン 講師: 烏山 昌起
********************
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
********************
来る7月17日より、XPERT公式セミナー「肩関節周囲炎に対する評価・治療~解剖・触診のポイントから病態に応じた病期別の対応まで~」を開催いたします
本セミナーは全5回のシリーズで構成され、肩関節周囲炎に対する評価と治療について網羅的に学ぶことができるオンラインセミナーです
肩関節周囲炎に対する評価と治療について学びたい方は、ぜひご参加ください
==============================
◾️概要
本セミナーでは、「肩関節周囲炎」に対する評価・治療について、解剖学や触診の知識を基盤としながら、病態に応じたアプローチ方法を病期別に整理し、臨床における実践力の向上を目指します
全5回にわたるシリーズ構成で、肩関節周囲炎への理解を段階的に深めていきます
第1回では、評価・治療において重要な「解剖学」の視点を取り上げ、臨床現場で活用できるポイントを解説します
第2回では、骨・筋・腱などの「触診」の技術を高めるための具体的なコツを紹介し、対象組織への正確なアプローチをサポートします
第3回では、肩関節周囲炎の「病態」を広い視野で捉えるための考え方を整理し、複雑な症例への対応力を養います
さらに第4回では、「炎症期」に絞って適切な評価法と治療戦略を解説し、急性期の症状を長引かせないための工夫を共有します
第5回では、「拘縮期」における関節可動域や日常生活動作の改善を図るための具体的な治療アプローチを紹介します
各回ともに、肩関節周囲炎の治療に関わる皆様が明日からの臨床で活かせる知識と技術の習得を目指します
◾️詳細※すべて開催後2週間のアーカイブ配信
【第1回】
・テーマ|肩関節周囲炎に対する評価や治療の根拠・視点を広げるための "解剖学" のポイント
・講師|河上 淳一先生(日本歯科大学 新潟生命歯学部 解剖学第1講座 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年7月17日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、どのような疾患でしょうか。日本肩関節学会は、可動域制限のある肩を「拘縮肩」、そのうち原因が特定できないものを「凍結肩」と定義しました(浜田 他,2021)。すなわち、明確な診断が難しく、病態も多岐にわたる疾患です。私たちは、まず対象となる構造を理解し、そこから患者に応じた評価と治療を行うことが求められます。しかし、教科書だけでは、三次元的かつ階層的なイメージの把握が難しい部位も少なくありません。本講演では、肩関節および肉眼解剖を専門とする立場から、「臨床現場に役立つ肩関節の解剖学」を解説します。次回の触診へとつながるよう、肩関節の構造理解を深めていただきたいと考えています。
(1) 肩関節の全体像
(2) 肩関節周囲の骨の特徴
(3) 肩関節筋の骨の特徴
(4) 肩関節関節包・靱帯の特徴
(5) 肩関節周囲の神経・血管の特徴
【第2回】
・テーマ|評価や治療を行う上で押さえておきたい骨・筋・腱・神経の "触診" のコツ
・講師|松本 伸一先生(古川宮田整形内科クリニック リハビリテーション科 理学療法士,医科学修士)
・日時|2025年7月31日 (木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎の診療においては、疼痛や可動域制限による機能障害が病期やその症状の程度によって求められる技術が変化します。肩甲上腕関節の運動のみでなく、肩関節複合体としての運動をとらえるためには、正確な骨運動をとらえるためのランドマークを把握することは必須の技術です。加えて、可動性が低下しやすい筋や神経の走行を理解することで、徒手療法や物理療法による介入の成果を改善し、長期の経過を良好にするために必要不可欠な運動指導やホームエクササイズを適切に指導することにもつながります。病態把握や評価・治療の精度を高めることに寄与する触診について、触診やエコー動画を交えながら理解を深めていきたいと思います。
1. 骨運動の触診
(1) 肩周囲のランドマークと触診のポイント
(2) 肩甲上腕関節の運動と触診
(3) 肩甲上腕リズムと触診(SHAに関連して)
2. 評価・治療に必要な筋・神経の触診
【第3回】
・テーマ|肩関節周囲炎の "病態" を包括的に捉える視点
・講師|隅田 涼平先生(福岡整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月7日(木)20:00〜21:30
肩関節周囲炎,いわゆる凍結肩(Frozen shoulder)は,「既知の肩関節疾患がないのに起こる肩の自動,他動可動域の著しい制限によって特徴づけられる原因不明の疾患」とされています(Zuckerman JD ,et al,2011).肩関節周囲炎患者の訴えで最も多いのが,疼痛と可動域制限ですが,その症状や病態は様々であり,どのように介入するべきか悩むことも多いのではないでしょうか.本セミナーでは,日頃,臨床で多く遭遇する肩関節周囲炎に関して,理解しておきたい病態や病期について解説し,どのように評価・介入を行なっていくべきか理解していただければと考えています.
(1) 肩関節周囲炎の定義
(2) 肩関節周囲炎の病態
(3) 肩関節周囲炎の病期
(4) 肩関節周囲炎に対する評価
(5) 肩関節周囲炎に対する理学療法の効果
【第4回】
・テーマ|"炎症期" を見極めるための評価と症状を長引かせないための治療のコツ
・講師|鶴田 崇先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士)
・日時|2025年8月19日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別され、好発年齢は40~60歳である。炎症期の症状は安静時も強い痛みがあり、動作時や夜間にまで増悪する。肩関節の自動運動は著しく制限され、睡眠障害を含んだ日常生活動作(ADL)の狭窄が生じる。滑膜の炎症反応が著明であり、積極的な理学療法を施すと炎症の助長を併発する恐れがある。よって、的確な理学評価と超音波機器装置などを利用した病態把握が重要であり、医師との治療方針とゴール設定の共有は大事である。
演者が臨床で各患者別に実施しているADL困難の把握方法、夜間痛に対する対処方法や活動量が多い疾患のADL拡大に繋がる評価と治療方法を紹介する。
1.炎症期の病態を理解する
1)肩関節周囲炎の病期の復習
2)炎症期に対する向き合い方
2.炎症期の病態を把握する
1)圧痛箇所による病態の把握
2)可動域制限因子の把握
3)肩甲胸郭のアライメント評価
4)姿勢および荷重変位の評価
5)カナダ作業遂行測定法(COPM)を利用した難渋しているADLの評価
3.炎症期に対する理学療法の紹介
1)各疾患に対するADL動作の紹介
2)各疾患に対するポジショニングの紹介
3)組織的過敏性を誘発させない治療戦略
4)炎症期でも可能な自主トレーニングの紹介
【第5回】
・テーマ|"拘縮期" の関節可動域・日常生活動作を拡大するためのコツ
・講師|烏山 昌起先生(南川整形外科病院 リハビリテーション科 理学療法士,医学博士)
・日時|2025年9月2日(火)20:00〜21:30
肩関節周囲炎は、炎症期・拘縮期・寛解期の3つの病期に大別される。炎症期を経た症例では、靱帯や関節包の線維化および瘢痕化により、生理的な弛み(遊び)が減少し、関節可動域や日常生活動作に制限が生じる。また、その上層に位置する筋腱組織でも伸張性の低下がみられるが、これには筋実質部自体の伸張性低下に加え、痛みに伴う筋収縮によって力が抜けない状態(筋緊張のコントロール不良)が混在しているのが現状である。したがって臨床では、肩関節運動の動作分析や制限因子の特定に加え、各組織の病態(短縮や攣縮など)を把握する視点も重要となる。
本セミナーでは、肩関節周囲炎の「拘縮期」に焦点を当て、演者が臨床で実践している各種評価方法(超音波評価を含む)を体系的に整理して紹介する。さらに、過敏性に応じた治療戦略を基盤に、筋短縮・筋攣縮および関節包に対する具体的なアプローチとその実際、運動療法の構成要素について解説し、より実践的な臨床応用を目指す。
1."拘縮期" の病態を理解する
(1)肩関節周囲炎における病期の復習
(2)”拘縮期"における治療対象組織
2."拘縮期"の病態を把握する
(1)肩関節痛のフローチャートによる評価
(2)姿勢および鎖骨・肩甲骨アライメントの評価
(3)肩甲上腕リズムの評価
(4)運動時痛のフローチャートによる評価
(5)肩甲上腕関節可動性と制限因子の評価
(6)筋短縮および筋攣縮の評価
(7)靱帯および関節包の評価
3."拘縮期"の病態に対する理学療法
(1)過敏性(Irritability levels)に応じた治療戦略
(2)筋短縮および筋攣縮に応じた治療戦略
(3)筋短縮および筋攣縮に対するアプローチの実際
(4)靱帯や関節包の伸張性低下に応じた治療戦略
(5)靱帯や関節包の伸張性低下に対するアプローチの実際
(6)運動療法の構成要素
(7)見落としやすい病態と対応の紹介
◾️受講目標
1. 肩関節周囲炎をみていく上で必要となる解剖学の知識を身につける
2. 肩関節周囲炎の評価・治療で必要となる骨・筋・腱の触診のポイントを理解する
3. 肩関節周囲炎の複雑な症状を病態の視点から把握する
4. 炎症期の症状に対応するために必要となる評価・治療の視点を理解する
5. 拘縮期に実践すべき評価・治療のポイントを理解する
◾️参加費
単回参加|1,980円(990円)
全回参加|6,600円(3,300円)
※()内の参加費はXPERT prime会員さま用の価格です
※prime会員の方はこちら( https://xpert.link/online-seminar/7932/ )からお申し込みください
※XPERTprimeへの入会はこちら( https://xpert.link/community/6290/ )からお願いします
◾️注意事項
・3日前以降にキャンセルされる場合はキャンセル料100%が発生しますのでご注意ください
・配布資料は各回の開催3日前にアップいたしますので、セミナーページ下部のダウンロードリンクからダウンロードください
・各回とも開催後2週間ご視聴いただける見逃し配信を予定しています
・見逃し配信の視聴用URLはセミナー終了後にメールにてお送りいたします
・キャリアメールをご利用の場合はメールが届かない場合がございますので、GmailやYahooメールなどのフリーアドレスへの変更をお願いいたします
・メールの受信設定をご確認いただき、「 info@xpert.link 」からのメールを受信できるよう変更をお願いいたします
・セミナー終了後2~3日経過しても見逃し配信の視聴用URLがメールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認いただき、それでも確認できない場合はセミナーページ下部の「セミナーに関するお問い合わせ」からご連絡ください
セミナーに関するお問い合わせ
この機能を利用するには、ログインが必要です。未登録の方は会員登録の上、ログインしてご利用ください。
講師プロフィール
肩関節の奥深さに触れ、久留米大学大学院にて修士(医科学)・博士(医学)を取得しました。肩関節のバイオメカニクスや筋骨格シミュレーションの臨床還元を日々模索しております。2024年より歯学部解剖学講座の教員となり、肉眼解剖学とバイオメカニクスの臨床の架け橋となるべく研鑽を積む毎日です。肩関節疾患の理解を深める一助となれるよう微力ながら努めて参ります。
Physical therapist / PhD / 理学療法士/博士(医学)/認定理学療法士(運動器)/専門理学療法士(基礎)/ Shoulder / Systematic review / Meta-analysis / 肩関節の臨床研究やレビュー研究を行っています。
過去のセミナーへのレビュー
西角暢修
セミナーを開催してみませんか?
XPERTでは、掲載手数料無料で、効果的な集客と効率的なセミナー開催が可能です。
また、XPERTではない外部サイトでの開催や、複数日程の開催、現地開催・オンライン開催の選択など、
様々な開催方法に対応し、スムーズなセミナーの集客・運営をサポートします。
- Feature01
セミナー掲載の手数料は無料
専門家の方々による、情報発信の機会を増やすために、XPERTではセミナー掲載の費用は無料としています。
- Feature02
セミナーの集客力アップ
専門家が多数登録しているため、ターゲットとなる方に効果的にアプローチでき、集客力アップが期待できます。
- Feature03
柔軟な開催方法を選択可能
XPERTでは、単日開催・複数日程の開催の選択や、現地・オンライン開催の選択など、様々な開催方法を提供しています。
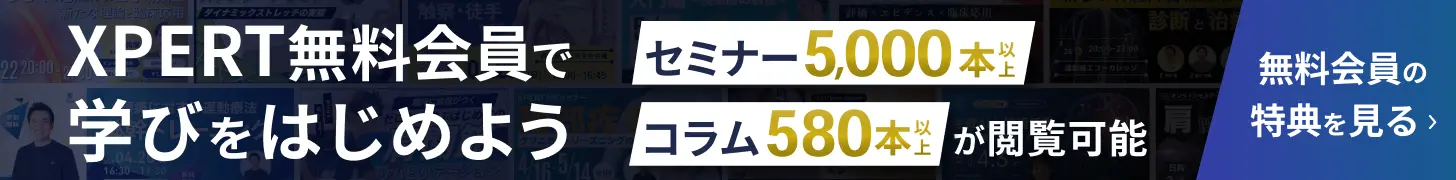
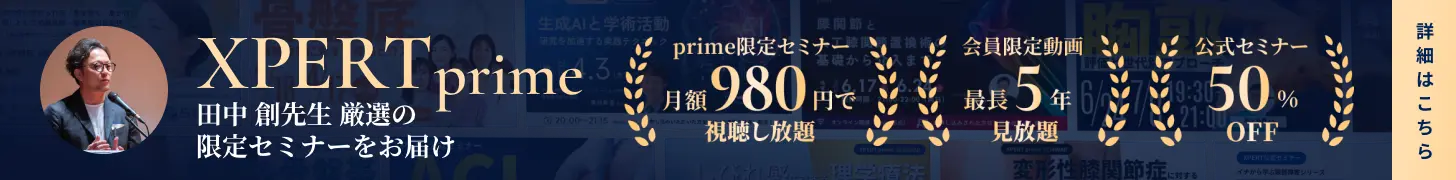
論文を見ただけではわからない評価方法の詳細や裏側が非常に面白かったです。こういうのがあると誤っ...