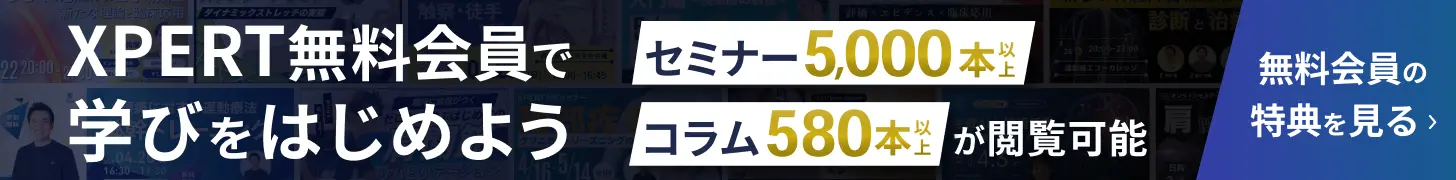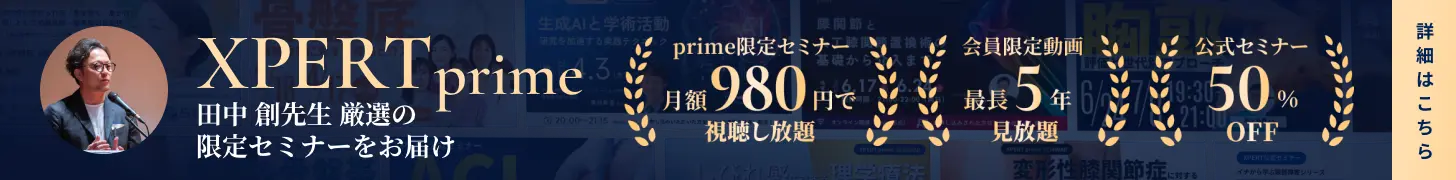■全額返金保証
内容にご納得いただけない場合は、料金を全額返金いたします。
※購入より1週間以内が対象となります
※決済・返金手数料はご負担いただきます
※受講はメルマガ登録が必要のため、代理登録を行います
ーーーーーーー
■充実のアフターフォロー
・2週間視聴可能な復習動画を配信
録画した復習用動画を2週間限定で公開します。セミナー終了後4日後までにお送りします。
・当日不参加でも、後日視聴可能
当日参加できない場合でも、復習用動画を視聴できるのでご安心下さい。
・受講後の質問にも継続して対応
オープンチャット機能を使用し、いつでも質問が可能です。
ーーーーーーー
【セラピストが知るべき歩行の進化的背景】
現代の研究が示すように、人間の直立二足歩行は進化の過程で直接的に獲得されたのではなく、まず直立姿勢への適応があり、その結果として二足歩行が可能になりました。
この知見は私たちセラピストに重要な示唆を与えてくれます。
それは、リハビリテーションにおいても、まず直立姿勢の獲得に焦点を当て、その後に歩行メカニズムの再確立を目指すべきだということです。
ーーーーーーー
【臨床実践のための7つの歩行メカニズム】
効果的な歩行リハビリテーションのためには、以下の7つのメカニズムが評価・治療の基盤となります。
1.初期接地時の関節配列と剛性制御
2.荷重応答期の衝撃吸収能力
3.荷重応答期における関節の動的安定化
4.全足底接地から立脚中期における重心の上前方への推進
5.立脚後期における股関節伸展
6.前額面での重心移動と制動機能
7.遊脚期のコントロール
効果的な歩行練習を行うためには、歩行において具体的にどの動作メカニズムに問題があるかを詳細に評価することから始めます。
その評価に基づき、特定された問題点に対応する運動要素を個別に取り出して集中的に練習します。
その後、これらの個別要素を全身にわたって動きが滑らかにつながるよう動作パターンとして定着させることが重要です。
今回は、進化的背景から直立二足歩行を可能にする機能的特徴を理解し、歩行を支える重要なバイオメカニクスの原理について説明します。
さらに、効果的なリハビリテーションの基礎となる「歩行を可能にする7つのメカニズム」の詳細を解説し、これらの知見に基づいたより効果的な歩行練習方法を提案したいと思います。
ーーーーーーー
◾️講義内容予定(※資料一部抜粋)
◇初期接地と剛性制御の評価
・初期接地における下肢関節の安定化
・踵接地時の足関節の背屈可動域の評価
・足底腱膜の短縮と下腿三頭筋の短縮
◇股関節の安定性の評価
・骨頭を臼蓋に引き寄せる筋群の機能不全
・骨盤のアライメント不良による臼蓋位置の問題
・骨盤前傾位で荷重を行い骨頭の前方変位が制動されるか評価
◇膝関節の伸展可動域の評価
・Screw Home Movement(膝関節のロッキング機構)
・伸展可動域制限とSHMの消失
・半膜様筋の評価と操作
◇荷重応答期の評価
・足関節と膝関節の衝撃吸収機構
・荷重応答期の下肢の鉛直配列
・大内転筋とハムストリングスの機能評価
◇重力に適応するための下肢の伸展活動
・股関節の伸展と推進
・大腿骨頭の前方変位
・体幹に起因する問題
など多数
開催日程
日時: 2025/05/25 (日) 14:00 - 17:00
開催場所: オンライン 講師: 石井慎一郎先生
こんな人におすすめ
留意事項
セミナーに関するお問い合わせ
この機能を利用するには、ログインが必要です。未登録の方は会員登録の上、ログインしてご利用ください。
講師プロフィール
【執筆図書】 「二関節筋の協調制御理論(重力が育てた運動制御のメカニズム)」医学書院(2021) 「膝関節機能障害のリハビリテーション (痛みの理学療法シリーズ)」羊土社(2022) 「運動学・神経学エビデンスと結ぶ脳卒中理学療法」中外医書(2022) 「問題解決モデルで見える理学療法臨床思考」 文光堂 (2022) 「運動からだ図解 リハビリで役立つ 動作分析の基本 新版」マイナビ出版(2024
セミナーを開催してみませんか?
XPERTでは、掲載手数料無料で、効果的な集客と効率的なセミナー開催が可能です。
また、XPERTではない外部サイトでの開催や、複数日程の開催、現地開催・オンライン開催の選択など、
様々な開催方法に対応し、スムーズなセミナーの集客・運営をサポートします。
- Feature01
セミナー掲載の手数料は無料
専門家の方々による、情報発信の機会を増やすために、XPERTではセミナー掲載の費用は無料としています。
- Feature02
セミナーの集客力アップ
専門家が多数登録しているため、ターゲットとなる方に効果的にアプローチでき、集客力アップが期待できます。
- Feature03
柔軟な開催方法を選択可能
XPERTでは、単日開催・複数日程の開催の選択や、現地・オンライン開催の選択など、様々な開催方法を提供しています。