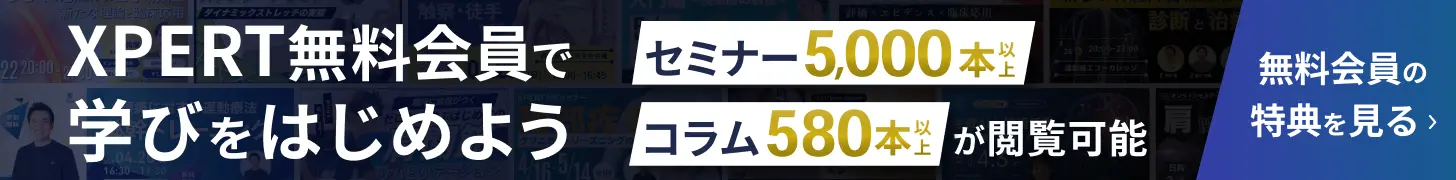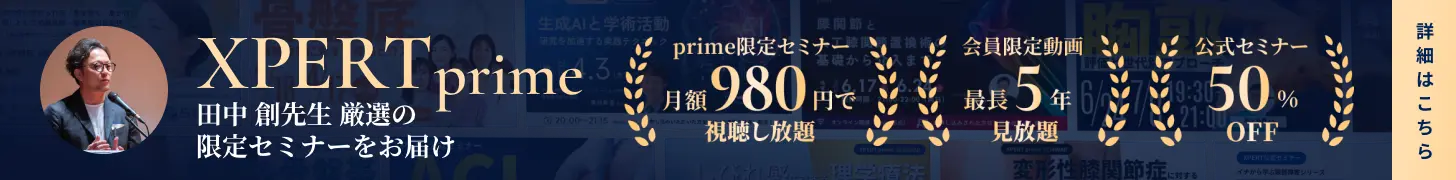【リピート配信:全3回】
・9月23日配信開始:第1回虚血性心疾患・心不全の病態とその医学的管理(22年1月26日開催分)
・10月1日配信開始:心不全に合併するフレイル・サルコペニアとその評価(22年2月26日開催分)
・10月10日配信開始:心不全に対する運動療法とリスク管理(22年3月26日開催分)
ー------------
【やった方がいいことより、やってはいけないことを知っておこう】
心臓リハビリテーションの患者を担当するセラピストには、常に大きな責任とリスクが伴います。
日本人の死因の第二位を占める心疾患ですが、心疾患のリスクに配慮し、適切に対応できるセラピストは、今後ますます求められていくでしょう。
高齢者の心不全の特徴の一つは、フレイル・サルコペニアとの関連が指摘されている点です。
心不全になると、息苦しさなどからあまり動かなくなり、筋力低下が起こり、サルコペニアの状態になります。
また、もともとフレイルで栄養状態が悪い人が心不全を起こすと、治療はますます困難となり、症状を改善させることが難しくなります。
さらにフレイルでは腎機能が低下し、心臓への負担が増大するため、むくみの原因になります。
このように、心不全とフレイル・サルコペニアは互いに悪影響を及ぼしあうため、心不全が軽症なうちから適切な対処をすることが重要です。
前回に開催した心不全の講義が分かりやすいと好評で、もっと深く理解する機会が欲しいとの声があったため、より深く理解していただけるよう3回講義としました。
心不全の評価と運動療法の全体像を理解し、リスク管理ができるようになっていただけるものと思います。
これを機に、リスクマネージメントの理解を深め、心不全のリハビリテーションを安心して行えるようになってください。
講義内容)
9月23日配信開始
【第1回】虚血性心疾患・心不全の病態とその医学的管理(22年1月26日開催分)
→循環システムとそのシステムが破綻した時の代償について初心者の方にもわかりやすくお話しします。
1) 循環機能の基本
・心機能の解剖生理
・循環の調節機能
・代償起点
・運動耐容能
・運動と心拍出量
・前負荷と後負荷
・前負荷と心不全
・心室リモデリング
・心筋梗塞、大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症
・慢性的な虚血による血管の反応
・心血管系の老化
・刺激伝導系と心電図
2) 虚血性心疾患・心不全の病態とその医学的管理
→虚血性心疾患・心不全の病態についての基本的な理解とそれらに対する医学的管理について解説します。
・急性冠症候群(ACS)
・心筋梗塞の経時的心電図変化
・Killipの分類
・高齢心不全患者の特徴
・心不全に罹患し急性増悪するまで
・急性心不全と慢性心不全
・収縮不全と拡張不全
・フランク・スターリングの法則
・心拍出量を増加させるメカニズム
・LVEFによる心不全分類
・左心不全と右心不全の特徴
・Forrester分類と治療方針
・心ポンプ機能低下時の代償機構
・急性心不全の初期対応から病態に応じた治療基本指針
・代表的薬剤の用法・用量,および副作用・注意点
・各ステージの治療目標
・心不全の病態と臓器合併症
10月1日配信開始
【第2回】心不全に対する運動療法とリスク管理(22年2月26日開催分)
1)総論(心不全、フレイル、サルコペニアについて)
・高齢心不全患者の特徴
・フレイルとサルコペニア
・フレイリティ・サイクル
・慢性心不全におけるミオパチー:エネルギー喪失の役割
・高齢者の虚弱化をもたらす要因とその影響
・必要エネルギー量の決定
・心不全予後関連因子と治療ターゲット
・サルコペニアに対する介入の考え方
・筋力に対する年齢とレジスタンストレーニングの影響
・膝屈筋のピークトルク値による心不全患者の生存
・活動レベルに応じた大腿四頭筋力の目標値
2)フレイルとサルコペニアの評価
・体的フレイル ・フレイルのスケール(各種)
・基本チェックリスト
・サルコペニアの診断基準
・体的フレイルとサルコペニアの共通点
10月10日配信開始
【第3回】心不全に対する運動療法とリスク管理(22年3月26日開催分)
1)身体所見の方法
・うっの覚症状
・低拍出量の覚症状
・尖拍動の位置
・外頚静脈怒張
・中静脈圧の推定法
・内頚静脈拍動の3つの特徴
・腹頚静脈試験
・浮腫について( 浮腫のグレード)
・チアノーゼの有無
・血圧検査
・脈について
2)心不全に対する運動療法とリスク管理
◇運動療法
・心不全、低ADL例のリハビリの流れ
・RM法
・レジスタンストレーニングの禁忌
・慢性心不全のレジスタンストレーニングプログラム
・有酸素運動のやり方
・運動強度をどうするか
・判断基準(息切れ、疲労感など指標を紹介)
・低運動耐容能の患者のリハビリの流れ
・禁忌
・運動負荷の中止基準
・負荷強度を下がる基準と症状
◇リスク管理
・普段から注意しておくべき評価項目
・問診で聞くこと
・理学所見(頚静脈圧、浮腫、息切れ、血圧、脈など)
・経過の把握
・前兆を捉える
◇症例検討
・心房細動ではどの程度までの心拍数まで許容できる?
開催日程
日時: 2022/10/01 (土) 08:00 - 20:00
参加費: 外部決済 講師: 松尾善美先生、西村真人先⽣
日時: 2022/10/14 (金) 00:00 - 12:00
参加費: 外部決済 講師: 松尾善美先生、西村真人先⽣
【リピート配信:全3回】
・9月23日配信開始:第1回虚血性心疾患・心不全の病態とその医学的管理(22年1月26日開催分)
・10月1日配信開始:心不全に合併するフレイル・サルコペニアとその評価(22年2月26日開催分)
・10月10日配信開始:心不全に対する運動療法とリスク管理(22年3月26日開催分)
ー------------
【やった方がいいことより、やってはいけないことを知っておこう】
心臓リハビリテーションの患者を担当するセラピストには、常に大きな責任とリスクが伴います。
日本人の死因の第二位を占める心疾患ですが、心疾患のリスクに配慮し、適切に対応できるセラピストは、今後ますます求められていくでしょう。
高齢者の心不全の特徴の一つは、フレイル・サルコペニアとの関連が指摘されている点です。
心不全になると、息苦しさなどからあまり動かなくなり、筋力低下が起こり、サルコペニアの状態になります。
また、もともとフレイルで栄養状態が悪い人が心不全を起こすと、治療はますます困難となり、症状を改善させることが難しくなります。
さらにフレイルでは腎機能が低下し、心臓への負担が増大するため、むくみの原因になります。
このように、心不全とフレイル・サルコペニアは互いに悪影響を及ぼしあうため、心不全が軽症なうちから適切な対処をすることが重要です。
前回に開催した心不全の講義が分かりやすいと好評で、もっと深く理解する機会が欲しいとの声があったため、より深く理解していただけるよう3回講義としました。
心不全の評価と運動療法の全体像を理解し、リスク管理ができるようになっていただけるものと思います。
これを機に、リスクマネージメントの理解を深め、心不全のリハビリテーションを安心して行えるようになってください。
講義内容)
9月23日配信開始
【第1回】虚血性心疾患・心不全の病態とその医学的管理(22年1月26日開催分)
→循環システムとそのシステムが破綻した時の代償について初心者の方にもわかりやすくお話しします。
1) 循環機能の基本
・心機能の解剖生理
・循環の調節機能
・代償起点
・運動耐容能
・運動と心拍出量
・前負荷と後負荷
・前負荷と心不全
・心室リモデリング
・心筋梗塞、大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症
・慢性的な虚血による血管の反応
・心血管系の老化
・刺激伝導系と心電図
2) 虚血性心疾患・心不全の病態とその医学的管理
→虚血性心疾患・心不全の病態についての基本的な理解とそれらに対する医学的管理について解説します。
・急性冠症候群(ACS)
・心筋梗塞の経時的心電図変化
・Killipの分類
・高齢心不全患者の特徴
・心不全に罹患し急性増悪するまで
・急性心不全と慢性心不全
・収縮不全と拡張不全
・フランク・スターリングの法則
・心拍出量を増加させるメカニズム
・LVEFによる心不全分類
・左心不全と右心不全の特徴
・Forrester分類と治療方針
・心ポンプ機能低下時の代償機構
・急性心不全の初期対応から病態に応じた治療基本指針
・代表的薬剤の用法・用量,および副作用・注意点
・各ステージの治療目標
・心不全の病態と臓器合併症
10月1日配信開始
【第2回】心不全に対する運動療法とリスク管理(22年2月26日開催分)
1)総論(心不全、フレイル、サルコペニアについて)
・高齢心不全患者の特徴
・フレイルとサルコペニア
・フレイリティ・サイクル
・慢性心不全におけるミオパチー:エネルギー喪失の役割
・高齢者の虚弱化をもたらす要因とその影響
・必要エネルギー量の決定
・心不全予後関連因子と治療ターゲット
・サルコペニアに対する介入の考え方
・筋力に対する年齢とレジスタンストレーニングの影響
・膝屈筋のピークトルク値による心不全患者の生存
・活動レベルに応じた大腿四頭筋力の目標値
2)フレイルとサルコペニアの評価
・体的フレイル ・フレイルのスケール(各種)
・基本チェックリスト
・サルコペニアの診断基準
・体的フレイルとサルコペニアの共通点
10月10日配信開始
【第3回】心不全に対する運動療法とリスク管理(22年3月26日開催分)
1)身体所見の方法
・うっの覚症状
・低拍出量の覚症状
・尖拍動の位置
・外頚静脈怒張
・中静脈圧の推定法
・内頚静脈拍動の3つの特徴
・腹頚静脈試験
・浮腫について( 浮腫のグレード)
・チアノーゼの有無
・血圧検査
・脈について
2)心不全に対する運動療法とリスク管理
◇運動療法
・心不全、低ADL例のリハビリの流れ
・RM法
・レジスタンストレーニングの禁忌
・慢性心不全のレジスタンストレーニングプログラム
・有酸素運動のやり方
・運動強度をどうするか
・判断基準(息切れ、疲労感など指標を紹介)
・低運動耐容能の患者のリハビリの流れ
・禁忌
・運動負荷の中止基準
・負荷強度を下がる基準と症状
◇リスク管理
・普段から注意しておくべき評価項目
・問診で聞くこと
・理学所見(頚静脈圧、浮腫、息切れ、血圧、脈など)
・経過の把握
・前兆を捉える
◇症例検討
・心房細動ではどの程度までの心拍数まで許容できる?
留意事項
セミナーに関するお問い合わせ
この機能を利用するには、ログインが必要です。未登録の方は会員登録の上、ログインしてご利用ください。
講師プロフィール
学歴) 1984年 国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院 理学療法学科卒業 2004年 神戸大学大学院医学系研究科保健学専攻 博士後期課程修了、博士(保健学)取得 講師著書・DVD等) 高齢心不全患者に対する理学療法 ※その他多数
学歴) 平成3年 国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院卒業 平成23年 神戸学院大学大学院 総合リハビリテーション学研究科修士課程修了 職歴) 平成3年~平成26年 岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科 平成26年~平成30 年大阪労災病院 中央リハビリテーション部 平成30年〜令和3年 山口労災病院 中央リハビリテーション部 令和3年~ 中国労災病院 中央リハビリテーション部
関連セミナー
セミナーを開催してみませんか?
XPERTでは、掲載手数料無料で、効果的な集客と効率的なセミナー開催が可能です。
また、XPERTではない外部サイトでの開催や、複数日程の開催、現地開催・オンライン開催の選択など、
様々な開催方法に対応し、スムーズなセミナーの集客・運営をサポートします。
- Feature01
セミナー掲載の手数料は無料
専門家の方々による、情報発信の機会を増やすために、XPERTではセミナー掲載の費用は無料としています。
- Feature02
セミナーの集客力アップ
専門家が多数登録しているため、ターゲットとなる方に効果的にアプローチでき、集客力アップが期待できます。
- Feature03
柔軟な開催方法を選択可能
XPERTでは、単日開催・複数日程の開催の選択や、現地・オンライン開催の選択など、様々な開催方法を提供しています。